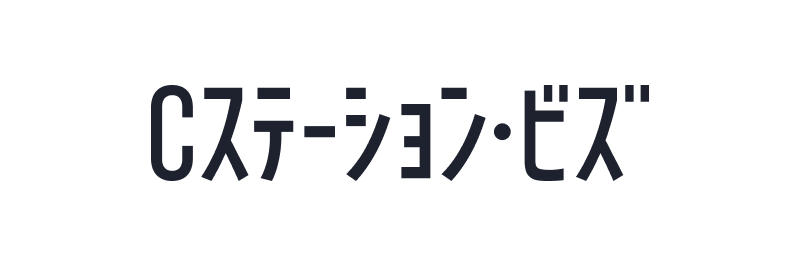7月19日は「知育菓子の日」。今回は、知育菓子を展開するメーカーであるクラシエ株式会社(以下、クラシエ)と、講談社の児童書『ねるねるねるねのおかしなおはなし』についてお伝えします。
「ねるねるねるね」のマーケティングを担当する、クラシエの木下優氏と、『ねるねるねるねのおかしなおはなし』を企画・編集した、講談社 児童図書出版部の澤有一良が対談。
企業が保有するキャラクターIPの価値、出版社だからこそできる企業のマーケティングへの関わり方、キャラクターIPと出版社のコンテンツ力を掛け合わせて生まれる新たなマーケティングの展開について、『ねるねるねるねのおかしなおはなし』本をつくる過程を語り合いました。
※知育菓子®はクラシエ株式会社の登録商標です。
※トップ写真:左から、クラシエ株式会社 フーズカンパニーマーケティング室 菓子部係長 木下優氏、株式会社講談社 児童図書出版部 澤 有一良
「ねるねるねるね」のキャラクターIPを活用する、初の試み
澤:今日はよろしくお願いします。初めに、「ねるねるねるね」はどのようなお菓子か、改めて教えていただけますか?
木下:「ねるねるねるね」は、1986年に誕生した知育菓子で、粉と水を混ぜると色が変わってふわふわふくらむのが特徴です。子どもたちが遊びながらお菓子作りができて、好奇心や探求心を養うことができます。ちなみに、知育菓子はクラシエの登録商標で、当社にはいま24種類の知育菓子があります。「ねるねるねるね」は、当社の知育菓子のエントリーブランドという位置づけになります。

クラシエの知育菓子のマーケティングを担当。「ねるねるねるね」は、2021年からブランド戦略に携わる。

子ども向けの文芸作品やエンタメ系作品の企画・編集を手掛けている。
澤:「ねるねるねるね」は、来年で、発売から40周年を迎えられますね。
木下:はい。40年を振り返ると、商品の売り上げに大きな波がありました。発売当時は、魔女のCMに象徴されるように「魔法のようなお菓子」というイメージを打ち出して、商品が爆発的に売れました。ところが時代が変わると、「体に悪そう」「子どもが食べて大丈夫なのか」といった声が上がるようになって……。お客さまの声を受けて、安全な素材を使っていることや、色が変わる仕組みを伝えるコミュニケーションに変えていきました。どのように商品を訴求すればよいか、現在も試行錯誤しています。
澤:パッケージには、商品キャラクターのねるねがプリントされています。ねるねが生まれたのは、2000年代でしたよね?
木下:2005年に「ねるねるねるね」のパッケージに初めて登場しました。
澤:現在は「ねるねるねるね」だけでなく、クラシエさんのすべての知育菓子のパッケージにねるねがいますね。
木下:はい。ねるねは、クラシエの知育菓子ブランドの象徴として、子ども達にも親しみを持ってもらい、盛り上げていく存在として育てていきたいと考えています。
澤:クラシエさんに児童書の企画をご提案させていただいたのは2023年でしたね。児童書についてどのようなものが売れているか市場調査をするなかで、お菓子やお菓子のキャラクターをモチーフにした物語に着目したのがきっかけです。菓子メーカーの中には、商品キャラクターが主人公の童話を制作し、シリーズ化するほどヒットしている例もありました。

子どもたちにとってお菓子はとても身近なものです。スーパーに行ったら、一目散にお菓子売り場を目指します。売り場でよく目にするお菓子やそのキャラクターが登場する児童書を作って、子どもたちに楽しんでもらえたら素敵だなと。「ねるねるねるね」は発売から40年近くもの歴史があり、親世代を含む多くの人に親しまれてきました。そこで、「ねるねるねるね」のキャラクターが登場する児童書の企画をクラシエさんに提案させていただきました。
木下:これまで当社では、「ねるねるねるね」のキャラクターにスポットを当てたキャラクターIPビジネスはおこなっていませんでした。澤さんからご提案いただいたような本を作る企画も初めてで。とても新鮮な企画で、社内では「ぜひやりたい」という声が多かったです。
書籍、映画。企業が持つキャラクターIP活用の流れは今後増えそう
澤:「ねるねるねるね」は世界観というものがきちんと構築されていますよね。「知育菓子」のウェブサイトには、ねるねやその仲間たちがいて、ねるねが暮らす「わくわくタウン」や、美味しいお菓子を開発するための「ねるねる研究所」がある。このような世界観は、いつ頃生まれたのですか?
木下: 私が「ねるねるねるね」を担当する前になりますが、2013年に広告会社などと協力して、ねるねやその仲間たちのキャラクター設定、世界観を考えたそうです。子どもたちが親しみを持って、共感・共鳴出来る継続性のあるコミュニケーションとして、現在もウェブサイトではマンガやアニメを展開しています。

澤:「ねるねるねるね」の世界観やキャラクターの個性が見えていたし、クラシエさんからのリクエストも明確だったので、コンセプトがブレることなく児童書を作り上げることができました。
木下:「ねるねるねるね」は、「色が変わってふくらむ」ことが一番の特徴です。この商品特徴にフォーカスして面白味を感じさせるものにしてほしいとリクエストさせていただきました。
澤:児童書を作るにあたり、大空なごむさんにお仕事をお願いしました。大空さんには、クラシエさんのリクエストや、すでに構築されている「ねるねるねるね」の世界観を踏まえた上で、オリジナリティを出してほしいとお願いしました。
『ねるねるねるねのおかしなおはなし』は、わくわくタウンにあるねるねる研究所で、ねるねとその仲間が、お菓子やおもちゃなどの研究をしている話です。ストーリーの中には、大空さんが考えたいろいろなお菓子が出てきたり、迷路やクイズもあったりして、楽しく学ぶことができます。
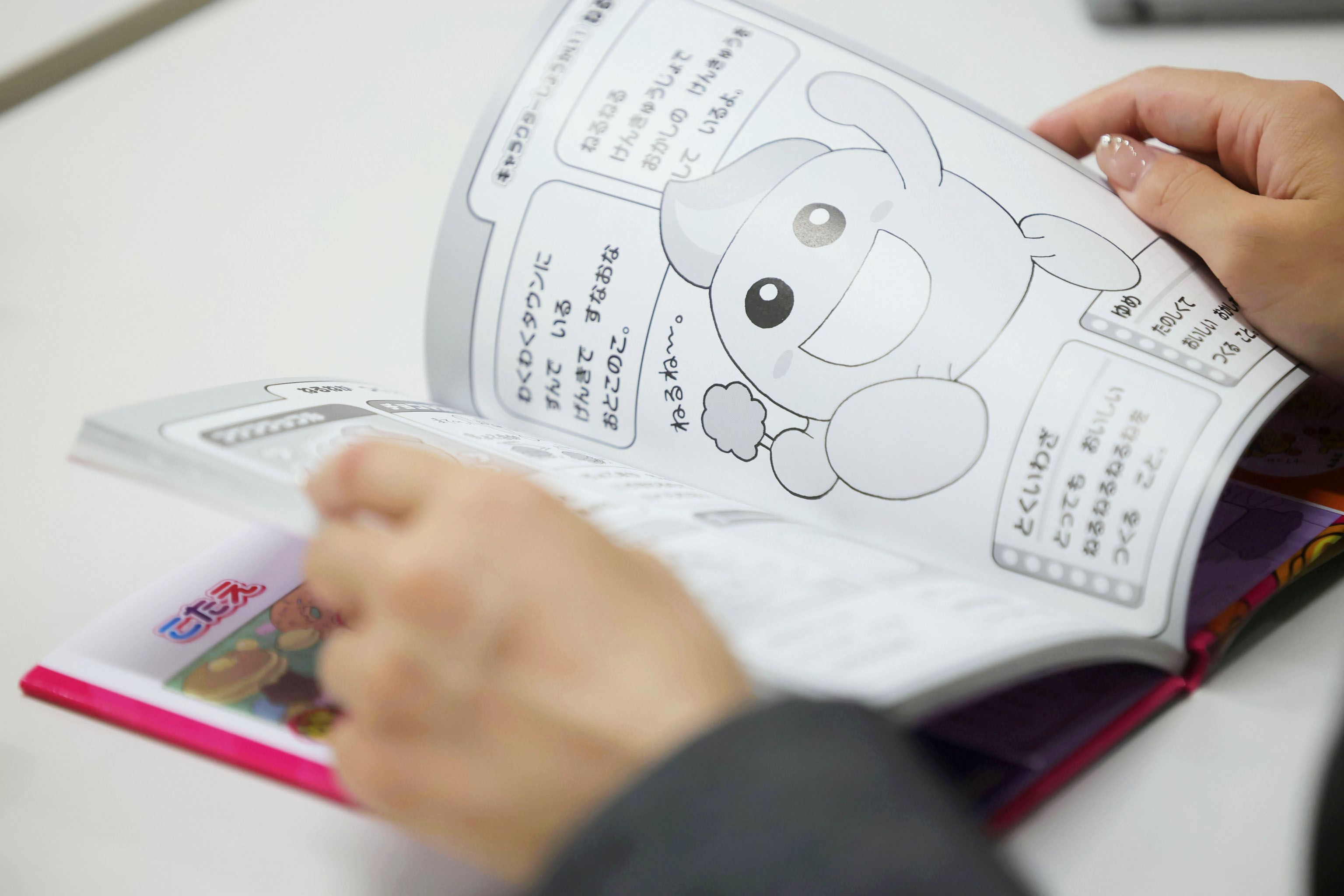
木下:出来上がった作品は、私たちの想像以上に、商品特徴やキャラクターの要素が盛り込まれてストーリー展開されていることに驚きました。とても新鮮で面白くて読み応えがありました。
澤:企業のキャラクターIPを児童書にするのは、弊社としても珍しく、他部署の人も興味を持っていました。読後には読者からの声も届きはじめています。
私は、今回制作した児童書のように、企業が持っているキャラクターIP活用の流れは今後増えていくと思っています。つい先ごろ、2025年5月に公開された映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」は大ヒットを記録しましたし。

木下:私も見ています。他社のお菓子のキャラクターも登場していて驚きましたし、映画を見てお菓子が食べたくなりました。
お菓子のマーケティングというと、例えば「ねるねるねるね」は、これまでテレビCMを筆頭に、保育園や幼稚園でのサンプルの配布や、購買キャンペーンを行ってきました。
しかし、私たちが講談社さんと作った児童書や、先ほど話題にでた映画は、全く違うアプローチです。特に知名度がある商品において、需要を伸ばすために、キャラクターIPを活用することはとても効果がありそうです。生活者は、商品を食べた経験があり、スーパーでも見かけるので、思い出してもらいやすいですよね。
澤:そうですね。木下さんがおっしゃるようなマーケティング視点もさることながら、書籍編集者としては、子どもたちが楽しめる作品を作ることが最も重要だと考えます。それで、結果的にマーケティングに寄与できるならうれしいことです。

書籍作りの経験と信頼感の上にできた作品
澤:企業のキャラクターIPを使って作品を作る意味を考てみると、当社が長年培ってきた書籍作りの経験と信頼感の上に、作品が出来上がるということだと思います。
いまは小さな子どももネットの動画を見るケースが多いですが、ネットの動画は広告が入ったり、親としては見せたくないものにたどり着いてしまうリスクもある。加えて、子どもたちに適切な内容かどうか、誰がどうジャッジしているのか分からないものもあります。
講談社など出版社には、未就学児や学童向けの絵本や童話を作ってきたノウハウがあり、校閲はじめ、事実確認や日本語の使い方、表現の適切さについて細かくチェックしています。自信を持って子どもに読ませられる質の高いものを作っているという自負があります。
木下:ストーリーのなかでちゃんと学べるという点でも、本という媒体は子どもたちにふさわしいですよね。私たち企業は、「本を作って学ぶ」というアプローチは、やろうと思ってもなかなかできることではありません。これまで商品と全く接点がなかった書店で、子どもたちにブランドアピールすることは、澤さんの提案がなければ実現できなかったと思います。
キャラクターが、顧客と商品というリアルなもの同士をつなげている
澤:私は、人気のあるユーチューバーの本も作っていますが、人気ユーチューバーはSNSでの拡散力がすごくて、瞬間的な告知効果があります。一方、ねるねのようなお菓子のキャラクターは、全国のスーパーなど、「リアルの場」での接触の機会が常にある。コンテンツの中にしか存在しないキャラクターは持ち得ない強みです。
お菓子以外でも、例えば、ある文具メーカーは、独自のキャラクターIPを作って展開しています。文具という個性を出しにくいカテゴリでマーケティングを考えるとき、キャラクターを自社で作る。そのキャラクターがSNSで人気になり、やがて本ができたりする。もうキャラクター単体でも収益化できるぐらいの勢いを感じます。もちろん、キャラクターが人気になれば商品が売れるという好循環が生まれるわけです。
木下:ファンにキャラクターでアプローチするという発想が似ていますね。
澤:文房具売り場も子どもたちが足を運びやすい場所ですよね。 売り場に子どもたちの目を引くキャラクターがいて人気になれば、マーケティングになります。ですから、企業がオリジナルのキャラクターを作る価値はあると感じます。
木下:「ねるねるねるね」のマーケティングに携わりはじめたときは、「どんな味が子どもたちに好まれるか」といったことや、「色が変わってふくらむことをどうパッケージで伝えるか」といったことに目を向けていました。ねるねはパッケージのどこかに入っていればいいという感じで、キャラクターへの意識は強くなかったのです。
でも、当社が出展する、千葉県幕張市にある仕事体験テーマパーク「Kandu(カンドゥー)」の、「ねるねるねるね」を体験できるコーナーにキャラクターの展示もしたのですが、視察に行ったとき、子どもたちが「ねるねだ!」と集まっているのを見て、キャラクターの力を実感しました。
ねるねの認知度は、他のお菓子のキャラクターに比べると高くないのですが、知育菓子が好きな子どもには、思った以上に認知度があることに気づきました。キャラクターを好きになってくれたら、商品をもっと好きになってくれるのではないか。それからキャラクターの重要性を意識し始めて、パッケージの中のキャラクターを配置する場所もよく考えるようになりました。
澤:木下さんがおっしゃるようにキャラクターIPには力がありますよね
とはいえ、企業のキャラクターIPの生かし方について、書籍編集者という立場からは、まだ手探りなところがあって……。今回、クラシエさんと、児童書『ねるねるねるねのおかしなおはなし』を作って一つ形ができたわけですが、今後も書籍と企業キャラクターIPの良い関係について模索していきたいと思います。本日はありがとうございました。

大空 なごむ (著), クラシエ株式会社 (原著) 講談社・刊 1430円(税込)